ものを拡大してみることのできる虫眼鏡(拡大鏡)自体が、最新技術だった時代から、顕微鏡は常に最先端でした。その後も細菌の発見やウィルスそのものを見ることができるようになり、顕微鏡は医学や生物学に大きな貢献をしてきました。さらには原子そのものを見ることができるようになった顕微鏡も登場し、その応用分野はますます、広がっています。また、新しい原理を応用した顕微鏡も次々に発表されています。
ここでは、なるべく平易な言葉で、主に、顕微鏡のうち、一般に顕微鏡といわれる光学顕微鏡の先端技術や用語を解説します。また、「光学顕微鏡の用語」では、光学顕微鏡を使い始めた方を対象に、特徴や意味を解説します。
顕微鏡の歴史
紀元前から存在したレンズと光学
虫眼鏡も顕微鏡の一種ととらえると、その歴史は大変古く、紀元前から存在し、イランの遺跡から水晶を研磨したレンズが発見されています。しかしこの時代の用途は、集光で太陽熱を集めるためだったようで、傷口を焼いてふさぐために医者が使用していたようです。
拡大鏡としての利用が始まったのは、11世紀以降でした。アラビア(エジプト)の科学者アルハーゼンがその著書「光学」の中で、ものの見える原理や眼の構造について発表し、その中で視力を補うレンズについて記述がありました。その本がラテン語に翻訳され、多くの修道士に読まれるようになり、ヨーロッパ各地で修道士によるレンズの製作が盛んになりました。13世紀には、書物の上に直接置いてルーペ(リーディングストーン)として使用されていました。
レンズが発展するのは、イタリアのベネチアで、それまでの色ガラスとは違う無色透明のガラスが盛んに作られる様になってからとされ、13世紀にはすでに眼鏡があったという記述も発見されています。
顕微鏡の発明は16世紀末のオランダ
顕微鏡の発明は、1590年頃、オランダのヤンセン親子が2つの凸レンズを組み合わせて、発明したとされています。望遠鏡を逆から覗いて、偶然発見したとされていますが、望遠鏡の発明はそれより20年ほど後とされています。ヤンセン親子が逆から覗いたのは、像が倒立して写る、現在、一般的に天体望遠鏡として使われているケプラー式望遠鏡です。天体を初めて望遠鏡で観察したガリレオが作ったのは、17世紀に発明された、像が倒立しない本来の望遠鏡(ガリレオ式望遠鏡)です。
バネのフックの法則で有名なロバート・フックは17世紀に顕微鏡を使って、微生物のなどを顕微鏡で観察したスケッチを発表しています。そのときの顕微鏡の倍率は最高でも150倍ほどだったといわれています。一方、フックがイギリスの王立協会に紹介したオランダのレーウェンフックは、自ら磨いたレンズ一枚の顕微鏡で200倍以上の倍率を実現しています。この、レーウェンフックの顕微鏡はプレパラート(試料を固定する観察用のガラス板)にレンズがついたようなものでした。このころ、レンズや素材のガラスについてはまだよく研究されておらず、一枚だけでも歪んで見えるレンズを二枚合わせると、像がよく見えなくなってしまいました。
現代の顕微鏡の確立と飛躍
レンズを複数くみあわせた現在のような顕微鏡が、発展するのは19世紀になってからでした。ドイツのカール・ツァイスは、物理学者のアッベやガラス職人のショットと協力し、6?700倍の倍率を実現し、医学や生物学に大きく貢献しました。19世紀末には、光学顕微鏡のほぼ限界まで性能が向上し、飛躍的な発展を遂げました。
その後、照明、偏光などの照明の工夫や、蛍光など試料加工の技術が発展しましたが、それまでの光学の延長上にありました。1950年代後半に研究され始めた共焦点顕微鏡は、解像度をあげる(より鮮明に見る)点と立体構造を知ることができる点で、それまでの顕微鏡とはちがっていました。
光学顕微鏡の限界を超える
一方、光学顕微鏡の解像度、分解能(拡大しても像がはっきり見える性能)は、光を使う以上、原理上の限界がありました。野口英世は黄熱病の原因を細菌と考えていましたが、実際にはウィルスで、光学顕微鏡では理論上発見することはできませんでした。そこで、登場するのが光を電子に置き換えた(透過型)電子顕微鏡、TEM です。電子は光より1000倍以上理論的な分解能が高く、百万分の1mm(1nm)の観察もできることなります。透過型電子顕微鏡は、1930年代にドイツで開発され、戦前の1938年には、すでにシーメンスから発売されていました。
同じ電子顕微鏡でも、走査型電子顕微鏡は、原理が違います。こちらは、レンズで画像を拡大するというより、電子線という、先端が非常に細い針(プローブ)で、試料表面をなぞり(走査)、その情報を画像にする走査型プローブ顕微鏡の原型ともいえます。試作は同じ頃に行われたにもかかわらず、その発展は、1960年代になってからでした。
最初の走査型プローブ顕微鏡(SPM)は、1983年にIBM・チューリッヒ研究所で世界で初めて原子像の観察に成功した走査型トンネル顕微鏡(STM)でした。原子の上をなぞった(走査した)のは、まさに針でした。
その後、SPMは、原子間力を利用するものも開発されています。また、走査型電子顕微鏡も電子で試料表面をなぞったときに得られる情報(特性エックス線、反射電子)を分析することにより、構成元素などを分析することもできるようになっています。走査から画像化にいたる処理は、コンピュータ、電子機器の飛躍的性能の向上がその発展の一端を担っています。
光学顕微鏡でも走査型ものが開発されています。先にあげた、共焦点蛍光顕微鏡やラマン顕微鏡も光を使った、広い意味で走査型プローブ顕微鏡ともいえるでしょう。また、近年、近接場光という特殊な光をみる顕微鏡も研究されています。
顕微鏡の構成要素
対物レンズ
試料の側にあるレンズで、これがないと拡大して観察することはできません。レーウェンフックの顕微鏡は対物レンズだけでした。初期の対物レンズは、 1枚だけでしたが、近年のレンズは、組み合わせレンズで、歪みの原因である収差を取り除いてあります。また、油浸レンズと呼ばれるレンズは、ガラスと同じ屈折率を持つ油をレンズと試料の間に満たして、空気とレンズの屈折の影響を排除する工夫がなされています。
収差の原因は、光が屈折すること自体やレンズの形状そのもにあります。
色収差:プリズムを思い出してください。ニュートンが太陽光(白色光)をプリズムに通して、光が虹色に分かれるのを発見しています。白色光はガラスを通るときに、その波長(色)によって、屈折する角度が違い、通る経路が違ってしまいます。レンズを通すと色がにじんでしまいます。
球面収差:最近までレンズの表面は球面でした。しかし球面では、周辺に入った平行光と、中心付近に入った平行光は、同じ1点には焦点を結びません。1点に焦点を結ぶようにすると、レンズの曲面は球面でなくなります。最近では、球面以外のレンズ(非球面レンズ)が設計できるようになり、CD やDVDのピックアップや眼鏡のレンズに応用されています。
収差は数枚のレンズを組み合わせて、小さくなるように設計されています。
電子顕微鏡では、電子を絞る電磁石が対物レンズになります。走査型プローブ隠微鏡には、レンズは使われません。
接眼レンズ
眼に近い方のレンズです。光学顕微鏡では、双眼になっているのでバイノキュラー、アイピースなどと呼ばれています。対物レンズに記されている倍率と接岸レンズの倍率を掛け合わせると顕微鏡の倍率が決まります。
最近では、CCDカメラを搭載するのも増えています。また、レーザー走査顕微鏡はなどは、CCDなどの検出器を通して画像を観察することになりますが、この場合は、検出器の前にあるレンズが接眼レンズとなります。
共焦点顕微鏡では接眼レンズの前に絞りを置いて、像がぼける原因となる周辺の光を排除しています。このままでは、1点しか見ることができないので、走査が必要になります。
透過型電子顕微鏡では、数段の電子レンズがあり、また、蛍光面に写った像を、別の拡大鏡で観察することもあります。走査型電子顕微鏡では、検出した電子で焦点をむすぶことは行われません。
照明
光学顕微鏡では、照明は重要な役割を果たしています。
もっとも一般的なのが明視野照明です。照明の光を対物レンズぎりぎりいっぱいに入るようにした照明で、余分な乱反射が少なくなります。透過では、試料の光の吸収率、反射では反射率によって、コントラストがつきます。
暗視野照明は、明視野とは逆に照明が対物レンズの周辺ぎりぎりだけの照明で、試料によって屈折、乱反射した光だけが対物レンズに入るようした照明方法です。
蛍光顕微鏡では、試料を特殊な染料で染め、蛍光を発生するようにします。蛍光は一定の波長の光(励起光)で照明することにより発します。その蛍光は励起光とは別の波長の光なので、フィルタで蛍光を励起光と分離することで、暗い視野の中に蛍光だけを観察することができます。
このほか、偏光、位相差など照明法もある。
試料
試料がないと、何も見られませんが、ただ、接眼レンズの前に置けばよいとは限りません。
上記なかでは、油浸レンズを使う場合は、油(エマルジョンオイル)の効果を発揮するため、プレパラートとして作成された試料でなければなりません。また、蛍光観察では蛍光物質をあらかじめ、含んでいない限り、蛍光染料で染める必要があります。コントラストをつけるために、染料で染めることもあります。
透過電子顕微鏡では、均一に電子を通すよう、精度よく非常に薄く試料をスライスする必要があり、専用の装置まであります。走査型電子顕微鏡では、電子線をあてた試料に電荷がたまらないように、金属でコーティングする必要があります。
最先端の顕微鏡
共焦点顕微鏡
点を理想的な顕微鏡で覗いても像は厳密には点になりません。点の周りに、ぼやけの原因となる輪が見えることになります。この輪を見えないように、絞りをおいたのが共焦点顕微鏡です。もう一つの特徴は、照明側も対物レンズをとおして、一点を照明することです。照明も像も共に焦点を結ぶので、共焦点顕微鏡と呼ばれています。しかし、これでは、一点しか見ることができないので、試料上をなぞる(走査)することが必要になります。さらに、焦点が上下(高さ方向)でずれると、照明の焦点もずれ、暗くなって見えなくなります。焦点の合ったところだけしか、明るく見えないので、立体的に試料を捉えることができます。
生物への応用では、蛍光染料で染めた試料を共焦点顕微鏡で観察することにより、蛍光でありがちな、ぼやっとした画像を、鮮明に、立体的に捉えることができるようになりました。レーザーで蛍光を励起し(光らせ)、蛍光だけをとらえるところは、非線形光学顕微鏡ににています。
ラマン顕微鏡
ラマン効果は、物質を光で照らした時に、その物質の状態(分子の運動状態)により、照らした波長とは違う波長の光がでてくる現象です。蛍光染料で染めなくても、励起光とは違う光が出ているのです。その光は非常に微弱で、強力なレーザーが登場するまで、実現しませんでした。
ある入射光に対して観測されるラマン散乱光は物質に特有で、散乱光のスペクトル(波長の分布)を調べることで、その物質を特定することができます。蛍光共焦点顕微鏡と構造は似たものになりますが、検出器に波長の分布を調べる装置が付きます。
非線形光学顕微鏡
非線形光学顕微鏡は、照明で照らした光以外の光をみる顕微鏡です。物質に光を当てると、反射や屈折がおきますが、ごく一部の光は、物質の状態によって波長が変わります。また、強い光をあてると、物質の状態がかわることもわかってきました。
第二高調波顕微鏡
第二高調波(SHG)は、入射光によって、物質から出てくる、入射光の2倍の周波数の光です。レーザーの波長を短くする(周波数をあげる)ことに、応用されている現象です。物質の微細構造によって、強度がかわり表面状態を知ることができる、入射光で選択的に照らした部分だけを見ることができるので立体構造を知ることができるなどの特徴があります。
CARS顕微鏡
CARSは、ラマン散乱のうち、入射光より周波数が高くなる光です。染色などをしなくても、蛍光を発する生体試料の観察がおこなえます。また、SHG顕微鏡同様、立体構造を知ることもできます。
電子顕微鏡
透過型電子顕微鏡(TEM)
光ではなく、電子を用いることで、原理的に分解能の限界を打ち破った顕微鏡です。照明に電子線を使い、光学レンズの代わりに、電磁石で電子線をまげる電子レンズを使用していますが、像を見る原理は光学顕微鏡と同じです。
走査型電子顕微鏡(SEM)
電子を用いることは、同じでも、走査型電子顕微鏡は、光学顕微鏡とは原理的に違います。どちらかというと、走査プローブ型顕微鏡に近い顕微鏡です。電子線という、非常に細い針(プローブ)で、試料表面をなぞり(走査)、そのときに得られる情報を画像にして、観察します。最初は、電子線によって、引き出させれる2次電子を観察していましたが、表面の組成がわかる、反射電子やX線なども検出できる様になり、分析装置としても発展しています。
走査プローブ型顕微鏡
走査型トンネル顕微鏡(STM)
プローブは針で、試料と針の間に、生じるトンネル効果によって精密に距離を測定しています。試料はピエゾ素子で精密に走査されていて、針が試料の上を一定の距離を保ちながら、なぞっていきます。試料の位置と針の位置が立体的にコンピュータで再現されます。
原子間力顕微鏡 (AFM)
STMはトンネル効果を測定するので、試料は電気を通す物質に限られましたが、原子間力顕微鏡は絶縁体でも、水中でも測定可能です。プローブはやはり針で、試料に針を限界まで近づけたときに、原子間力で針が動くのを検知して、高さ方向の距離を測定します。試料の走査はピエゾ素子で精密に走査され、STM と同様に、試料の位置と針の位置が立体的にコンピュータで再現されます。
光学顕微鏡による観察
ここでは、顕微鏡をもっとよく知ってもらうために、代表的な光学顕微鏡による観察について紹介します。
明視野観察
最も一般的な方法で、学校でだれでも一度はこの方法で顕微鏡を見ているでしょう。透過の観察では、サンプルは明るい背景の中に見えます。
試料を一様に照らし、透過率や反射率の違い(色と言ってもよいでしょう)によって、像のコントラストを得る観察です。普段われわれが物を見るときと同じです。
しかし、生物などの場合、多くの試料は、透明で色がほとんど無く、透過で見ると、はっきりしたコントラストがでません。このため、試料に色を付ける染色手法も発展しました。
透過観察では試料に対して、対物レンズの反対側に照明装置がおかれ、対物レンズいっぱいに照明光が入るように調整します。このため、視野の背景は文字通り明るく見えます。金属顕微鏡など反射光で観察する場合は、対物レンズを照明用のレンズとして使う、落斜照明が行われます。
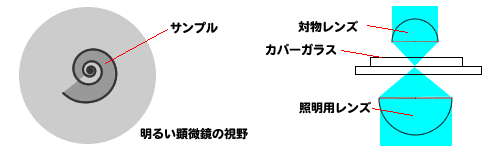
暗視野観察
明視野観察では、はっきりしない透明で色のないサンプルを、照明方法を変えて改善しようとする手法です。大まかには、明視野では正面からであった照明を斜めから当てる観察方法です。
照明レンズの前に中心を隠すリング状のスリットをおきます。照明光は周辺部分からだけとなり、斜めの光が試料にあたります。試料のないところでは、照明は対物レンズにほとんど入らずに、背景は暗くなります。試料のあるところでは、照明光の方向が、反射や、透過では屈折で、方向が変わり対物レンズに入るようになります。このような試料上の一部が明るく見えることになります。明視野で見えにくかったサンプルにコントラストがついて、見える可能性があります。染色してサンプルを加工しなくて済む訳です。解像度がよくなるわけではありませんが、一様な表面に分解能ぎりぎりの非常に小さい物体があるような場合、見つけやすくなる可能性もあります。

位相差観察
透過の試料を染色せずによく見るための工夫です。暗視野観察をさらに進めた方式ともいえます。
透過観察で、試料上とそうでない部分を通った光では、位相がずれています。これは物質によって光の伝わる速度が変わるためです(回折や屈折の原因)。しかし、物質の有無によって生じたこの位相差は人間の眼では感じることはできず、何も見えません。そこで、この位相がずれた光を干渉さで明暗に変えて観察するのが、この方法です。
具体的には、特殊な照明と対物レンズをセットでつかいます。照明にはスリット(リングスリット)があり、リング状に照明をおこないます。暗視野照明と似ていますが、暗視野照明では照明光が対物レンズぎりぎりを通すようにするのと違い、位相差観察では新たに追加するリング状の位相膜に照明が当たるようにします。
サンプルを通過した光は、試料が小さい(透過する距離が短い)場合、4分の1以下の波長だけ、回折によって遅れ、しかも方向がかわるので、位相膜のないところを通過します。サンプルがないところでは、照明光は、位相膜の部分を通過し、それによって、位相が4分の1波長だけ進みます。-1/4 と+1/4で二つを干渉させると、1/2、半波長ずれた逆位相でお互いに打ちしあい、暗くみえます。何もないところでは、干渉はおきないので、背景が明るい明視野のようにみえることになります。
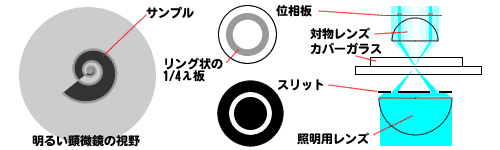
微分干渉観察
干渉させて明暗を見る点では位相差法と同じですが、回折ではなく、光路差(光の進む距離)で干渉をおこす方法です。白色光を使った場合は、ニュートンリングの様な虹色が出ます。
薄膜や微細な隙間では、表面とその下の面で反射した光が、光路差の違いで干渉して虹色の縞ができます。単色光では濃淡の縞になります。もっとも明るくなる部分ともっとも暗くなる部分の光路差は波長の半分ですから、一つの縞で数百nm(1波長分)の高低差を見せることができます。
微分干渉では、ノマルスキープリズムが使われます。このプリズムを通った直線偏光は直交する2つの偏光にわかれます。しかも、少しずれます。この光を照明としますが、サンプル上で干渉はおこりません。対物レンズの後にも、同じプリズムをおくと、分かれた偏光は元に戻り、干渉させることができます。
分かれた2つの照明光は試料を透過しますが、立体的な構造があれば、試料の中を通る距離が違い、光路差の違いで位相差が生じます。対物レンズの後ろでこの位相差に応じて干渉による濃淡が生じます。
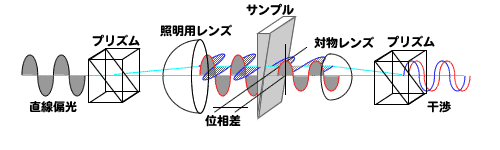
偏光観察
試料によってはその構成する物質によって、偏光を変えるものがあります。これを利用して、偏光した照明でサンプルをてらし、対物レンズのあとにある偏光板をまわして、偏光の様子を像で見るのが、偏光観察です。
対物レンズのあとにある偏光板の方向と、試料からの偏光が平行なら明るく、直交するなら暗くみえます。液晶物質はもともと透明なので、普通の観察法ではみえません。そこで、偏光で観察します。また、半導体素子の故障解析法として、故障部分が加熱する様子を表面にたらした液晶が対流し、偏光が変わることで視覚化する方法もあります。また、透明樹脂に力を加えると、その様子が偏光の違いとしてとらえられることも知られています。鉱物、氷などの結晶の観察にもよく用いられています。
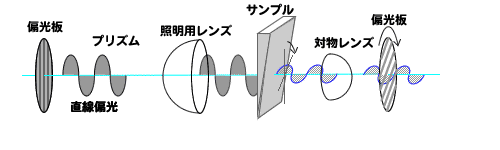
蛍光観察
試料を蛍光染料で染めて観察する方法です。自然界の中にはそのままでも蛍光を発する物質は多く、タバコの葉など、そのまま観察できる物もあります。
通常、蛍光観察では紫外線など短い波長の光で照明します(励起光)。蛍光を発生する物質は、その光を吸収し、励起状態になり、その状態から元に戻るときに、励起光よりも長い波長の光(緑)を出します。そのため、一定波長以上の光だけを通すフィルタを対物レンズの後におけば、照明の光はみえません。この場合は、紫外光を通さないフィルタです。真っ暗な背景に蛍光部分だけがみえるので、見やすくなる特徴があります。
照明光は水銀ランプなどの光を特定波長だけを通すフィルタをとおして作り出します。
生物分野では、共焦点顕微鏡と組み合わせて、より鮮明に、さらに立体構造まで読み取ることができるようになりました。
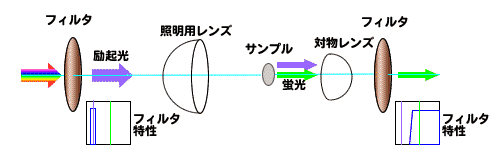
光学顕微鏡の用語
ここでは、よく眼にする、あるいは、耳にする顕微鏡用語について、もっとよく知ってもらうために、解説します。
倍率
10ミクロンの試料が10ミリに見えれば、倍率は1000倍になります。
写真にすれば、定規を当てられるので、はっきりします。写真上で10 mm に写っている10μmの物体は、1000倍です。
観察しているときの倍率は、対物レンズにかかれている倍率と接眼レンズにかかれている倍率をかければ顕微鏡の倍率にはなります。顕微鏡に会った対物レンズと接眼レンズを使用している限り、この倍率は正しく計算されます。(そのように設計されています。)
顕微鏡には、メーカーによって、鏡筒の長さが、160mmのもの、210mmのものなどがあります。接眼レンズと、対物レンズはこの距離に合うように作られています。倍率はこの設計仕様にあっている場合ですので、違う設定の対物レンズを使えば、倍率は違ってきます。他にも最高の画像、性能が得られる様、2つのレンズは設計されているので、理由もわからず、いろいろなメーカーのレンズを混ぜて使用することはあまり、勧められません。
倍率は、単に、どれだけ引き延ばしたかという意味ですので、画像が鮮明かどうかの尺度ではありません。拡大だけなら、簡単におこなえますので、鮮明さを無視して引き延ばすことを「バカ倍」ともいいます。デジカメで撮った山の風景写真を、どんどん引き伸ばしても、山に生えた木の葉が見えるわけではなく、ぼやけて、何が写っているのかわからなくなります。

油浸レンズ
通常、倍率の表記の下に線の入った対物レンズです。「OIL」などともかかれています。
このレンズはガラス程度の屈折率を持つ油をレンズと試料の間に満たして、空気とレンズの屈折の影響を排除する工夫がなされています。従って、油を使用しない場合は、性能を十分に発揮できません。
普通のレンズでは、レンズ(ガラス)→空気→カバーガラスと2ヶ所で光を通る媒質が変わり、屈折がおこります。油浸レンズで使用する油、イマージョンオイルは、ガラスと屈折率が合わせてあるため、屈折がおきません。ガラスの中に試料が取り込まれている感覚です。このことは、開口数を大きくすることにつながり、ひいては、解像度を上げることになります。
油浸レンズはその性能の高さから、半導体の露光装置にも応用されるようになっています。また、電子顕微鏡など、光を使用しないレンズでも、同じような働きをする電子レンズを油浸レンズと呼んでいます。

開口数(NA)
開口数は解像度をきめる数値です。対物レンズの焦点から、対物レンズにいっぱいに広がった円錐形の角度をθとするとnsinθで表されるのが、NA、開口数です。ここでnは対物レンズと試料の間の物質の屈折率です。
直感的には、どれだけ広く、試料からの光をとりこめるかということになります。レンズには開口数も表記されていて、高性能な対物レンズで0.95ぐらいの数字です。
空気の屈折率は1ですので、NAも1を超えることはありません。逆にnを1以上にすれば、もっと大きな開口数が得られます。対物レンズと試料の間に空気より屈折率の高い油などを充填することで、NAを大きくしているのが、油浸レンズです。油浸レンズの開口数は1より大きく、1.40もあるものもあります。開口数が1以上であるというのは、θが90°でNA=1ですから、直感的には、対物レンズと反対方向に反射した光も拾い集めてくる感覚です。
解像度の限界は空気中では 波長 / 2NA となり、開口数が大きいほど、解像度は小さな数値、つまり、より細かいものを見えることになります。また、NAの大きなレンズはどうしても作動距離が短くなります。
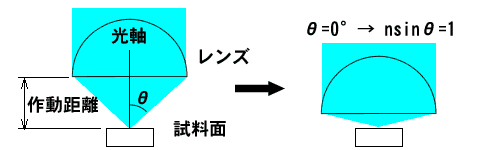
解像度
どのくらい小さいものがみえるかの目安になる数値です。倍率はどんどん引き延ばせば、大きくできますが、解像度が十分になければ、引き延ばしたときにぼやけてしまいます。カメラ付き携帯の画像を大きく引き伸ばすとぼけぼけの写真になるのは、このためです。
分解能ともいわれますが、顕微鏡では、その装置で、2つに見分けることのできる、2つの線(点)の最小の距離が解像度となります。1ミクロンの解像度とは、1ミクロン間隔の2本の線が、2本に見えるということです。この距離が小さいほど、「分解能が高い」「高解像度である」といいます。
画素数も解像度とは別の特徴をあらわす数値です。いくら500万画素のデジタルカメラでも解像度がなければ、ぼけた写真しかとれません。しかし、普通は、大きな画素数に合わせた解像度の高いレンズがついているはずです。
間隔dのスリットがぎりぎりで判別できるとき、その解像度がdとなります。スリットを通る光は、dが小さくなると、回折して分かれてしまいます。まっすぐ通り抜けてきた光(0次)は、間隔をかえても、いつも見える光です。少なくとも一番低い次数の回折光(±1次)が、レンズに入らないと、スリットであることはわかりません。このときの回折光の角度θは、波長をλとすると、dsinθ=λとなります。この角度は開口数NAの定義と同じですので、d=λ/NAとなります。波長が小さいほど、開口数NAが大きいほど、dは小さくなり、高い解像度が得られることがわかります。
上記の説明は、照明が垂直に当たった場合ですが、実際には、照明は斜めからも当たるので、照明の仕方も解像度に影響を与えることがわかります。理想的には、照明を同じレンズで行えば、2倍の解像度が得られるため、解像度の限界はλ/2NAとなります。
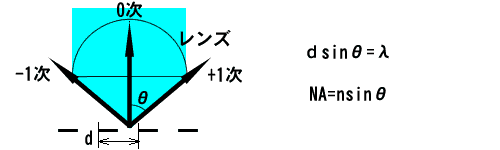
収差
薄いレンズや焦点距離の長いレンズでは、大きく屈折せず、光は、ほぼ焦点に集まりますが、一般には、理想的な焦点からずれています。このずれを収差といい、像がぼやける原因になります。収差の原因は、光が屈折すること自体やレンズの形状そのもにあります。
色収差:太陽光(白色光)をプリズムに通して、光が虹色に分かれるとおり、白色光はガラスを通るときに、その波長(色)によって、屈折する角度が違い、通る経路が違ってしまいます。レンズを通すと色がにじんでしまいます。
球面収差:普通のレンズの表面は球面で、周辺に入った平行光と、中心付近に入った平行光は同じ1点には焦点を結びません。焦点が1点に結ぶのは放物面鏡です。そこで、CDやDVDの光ピックアップには、この歪みが最小になるように各部分の曲面を設計した非球面のレンズが使われています。顕微鏡では、屈折率の高いレンズで、曲率を小さくしたり、2枚のレンズを使って1枚当たりの曲率を小さくして影響を低減しています。
このほかに、周辺部の画像がぼやけてしまうコマ収差、光軸の外からの光線に発生する非点収差、像が平面にできず曲面にできる像面湾曲、画面の周辺部で直線が樽型に曲ってしまう歪曲収差などがあります。
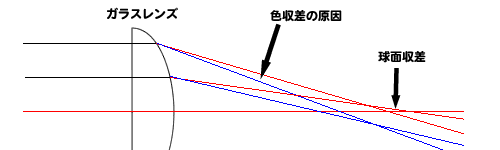
収差は、ガラスの素材を変える、逆の性質を持ったレンズを組み合わせて打ち消し合うなど、数枚のレンズを使って小さくなるように設計されています。顕微鏡の対物レンズには、この補正のされ方により、「アクロマート」「アポアクロマート」「プランアポアクロマート」などのレンズがあります。
アクロマートは2色(赤と青)だけに対して色収差が取り除かれているので、ピントがあっても多少の色がにじんでしまいます。しかし、単色光でモノクロの写真をとるのであれば、十分といえます。アポクロマートは3色の色収差をとりのぞいたもので、プランアクロマートはアクロマートの像面湾曲を補正したレンズです。プラン系のレンズは視野全体を写真やCCDで歪みなく、とらえることができます。そして、プランアポクロマートは前述2つの性能をもったレンズで、当然、高価なレンズとなります。
焦点深度
サンプルにピントを合わせたとき、焦点面には像ができています。その焦点面を移動させても像が許容できる(ぼけない)距離を焦点深度と言います。焦点深度は開口数に反比例するので、分解能を高く、かつ、焦点深度を深く、という訳にはいきません。ふつう、倍率が高くなると開口数が大きくなり、解像度があがり、焦点深度は浅くなります。また写真撮影においての焦点深度は肉眼での観察の約半分ほどしかなく、肉眼でのピント合わせ以上に、写真撮影のピント合わせは難しくなります。CCDではさらに、焦点深度が小さくなりますが、モニターを見ながら焦点を合わせられるので、気にならないかもしれません。
これに対して、ピントが合っている状態で、サンプルを移動させてもぼけない距離を被写界焦点深度と言います。被写界深度内にあるものは同時に見えることになります。被写界深度も開口数に反比例します。
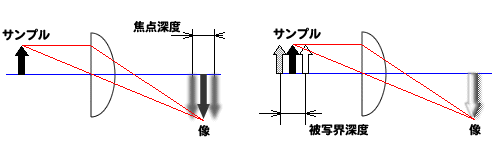
共焦点顕微鏡は、被写界深度が通常の顕微鏡より小さくなりますが、ピントが合った部分だけが明るくなります。これを利用して、サンプルを光軸方向にずらしながら(Z方向のスキャン)、輝度の最大値だけを記録すると、原理的に被写界深度が無限大の像を作り出すことができます。最近の画像処理装置の中には、ピントの合った画像だけを選び出して合成し、同様の機能を実現するものも出てきています。