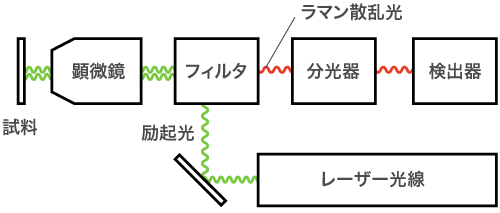1928年、インドのC.V.Raman博士によって発見
ラマン分光法のもとになるラマン効果の歴史は古く、1928年、後にノーベル賞を受賞したインドの Raman 博士によって発見されました。しかし、散乱光の強度が入射光(励起光)に対して非常に微弱なため、1960年代のレーザの発明までは、ラマン分光に実用的な光源がありませんでした。
1970年代後半には光学顕微鏡にラマン分光装置を搭載した顕微ラマンが登場し、局所的な分析手段として多分野で使用されるようになりました。しかし、80年代に赤外吸収法がフーリエ変換によって著しく進歩した結果、測定の難しいラマン分光法は、あまり利用されない時期が続きました。
その後、デジタルカメラやビデオカメラに使用されるCCDの進歩による検出器の性能向上で、一度にスペクトル分析結果が得られるようになり、大幅な測定時間の短縮が可能になりました。また、分光器の発展により装置が小型化し、性能が向上し、保守も簡略化され、レイリー散乱光(迷光)の除去フィルターが進歩し、感度が向上したことなどにより、ラマン分光法も赤外吸収と同様に、多くの分野で研究者が着目する分析法となりました。